かつて昭和の時代には1つの会社に勤め続けるのが当たり前の時代でしたが、今や転職や退職が珍しくない時代となりました。
退職理由にはバリバリ活躍したい人やスキルを高めたい人など前向きな退職をする人もいる一方で、人間関係が悪かったり、給料が低かったり、自分の時間が取れないといった不満で退職する人が多いです。
しかし、どちらにせよ初めての退職で何をどうしてよいかわからない場合がありますよね。
一般的なマナーを順守したうえで、トラブルを起こさずに円満に退職するのが理想です。
今回は会社を退職を検討している方に向けてその手順を解説していきます。特に新卒で入社して初めての退職を検討している方には右も左も分からないと思いますので、是非参考にしていただきたいです。
一般的な退職の手順は7つ
基本的な退職の手順は下記のようになっています。
①退職の意志を上司に伝える
②退職日と最終出勤日を決める
③後任に業務の引き継ぎをする
④身の回りの整理整頓をする
⑤取引先や社内関係者に挨拶しておく
⑥会社に提出物と返却物を渡す
⑦有給休暇を申請する
①退職の意志を上司に伝える

退職の意志を持っているけれど、現時点でまだ会社に伝えていない場合について記載します。
特に新卒で入社して初めて退職する方はその意志をいつ・誰に・どのように伝えるのかがわからないと思います。
【いつ】法律上は2週間前、一般的には3~1ヶ月前
民法上では雇用期間の定めがない正社員なら退職の意思を2週間前に伝えれば問題ないです。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
引用:WIKIBOOKS
ただし、一般的には2週間前に退職の意志を伝えた場合は後任の人員補充や引き継ぎの期間が難しいので、会社から引き止められることがケースがあります。
円満退職を望むなら約3か月~1か月前が無難な選択だと思います。それでも不安ならば就労規則に記載されている内容を確認してその期間内に申し出ると良いでしょう。
よくあるのが「今は忙しいから無理だ」「業務に支障をきたすから損害賠償を請求してやる」「社長から許可がないと駄目だ」などと退職を申し出を断るようなことを言ってくることがあります。
しかし、退職する権限は当事者である従業員にあるので、会社側がどんなことを言ってこようが法律上確実に辞めることが可能です。ただ、業務に支障をきたさない程度に引き継ぎを終わらせられる余裕のある期間を設けたうえで伝えるのが一般的なマナーになるでしょう。
【誰に】直属の上司に伝える
まず最初の一歩として退職の意志を伝えることになりますが、誰に伝えるかが非常に悩む部分ではあります。
一般的には直属の上司に退職の意志を伝えることになっています。ただ、どうしても言いづらい関係の場合には上司の上司、またはその課や部署で一番偉い人でも大丈夫です。
ここで注意したいのが、事務所など従業員のいる中でいきなり退職の意志を伝えるのはまずいことです。
上司に「お話したいことがあるのでお時間いただけますか?」とアポを取り会議室などの別室で話すのがマナーとなっていますので、まずは話し合いの場を設けて下さい。
この時に会社的には辞められると困るので上司からは引き止められたり、別の話ではぐらかされると思いますが、退職の意志を決めているならはっきりと伝えましょう。
職業選択の自由を阻害する行為は憲法第22条に違反することになりますので、これを知っているだけでもいつでも行使できますし、最終手段として使うのも手です。
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
引用:Wikipedia
【どのように】退職届(退職願)を書いて伝える
上司に退職を伝える際には退職届または退職願を用意しておき、口頭と書面の両方で伝えると良いです。
口頭だけでは退職の意志が弱い印象を与えてしまい引き止められることになりますし、言った言わないのトラブルに発展する可能性があります。
また、退職届(退職願)を提出したのにもかかわらず、うやむやにされたり、破棄されたりする恐れもあるのでコピーをとって手元に残すこともしておきましょう。
因みに「退職届」は「退職します」と退職を申し出る書面です。申し出たら退職の撤回はできなくなりますので、どうしても辞める強い意志表示にはこちらが適しています。
一方で「退職願」は「退職したいです」と申し出て、会社の承認を求める書面です。トラブルを起こさず穏便に退職の段取りを進めたいならこちらが適しています。
②退職日と最終出勤日を決める

退職の意志を伝えて上司が了承したら退職日と最終出勤日を決めることになります。
あなたが正社員であるなら退職日は申し入れの日から14日後に可能で、先に述べた通り民法第627条に定められているからです。
ここで注意したい点が下記になります。
- 完全月給制の人は当月前半申し入れ、翌月退職 (民法第627条2項)
- 6か月以上の期間を定めた報酬制の人は3か月前申し入れ、3か月後退職
(民法第627条3項) - 有期雇用の人は契約期間中は基本退職できない、1年以上勤務ならいつでも退職可 (労働基準法第137条)
これらに当て余る人はくれぐれも注意して退職日と最終出勤日を決めて下さい。
ただし、一般的としては後任の引継ぎに余裕のある期間を見定めてそれらを設定することになりますので「今すぐにでも退職したい!」ということがなければ引継ぎが終わる期間を目途に話し合ってみましょう。
また、ここであなたに有給休暇が14日以上ある場合には退職の申し入れの翌日から会社に行かなくても法律的には特に問題はないです。
③後任に業務の引き継ぎをする

次に後任に業務の引き継ぎをすることになりますが、これに関しては業務の内容によって引き継ぎに掛かる時間や決まり事が変わってきます。
ただ、どの業務でも言えることですが、大切な事はきちんと引き継ぐ事です。
いい加減に引き継ぎをしてしまうと事故やトラブルを招いて後任に迷惑を掛けてしまい、最悪の場合は損害賠償になるかもしれません。
また、引き継ぎ内容を明確にするために「引継書」を用意するように定めている会社もあります。
④身の回りの整理整頓をする

退職日が決まり引き継ぎ期間に入ったら自分の持ち場の不要な書類や道具、私物を整理整頓していきましょう。
仕事で使っていた書類や道具は勝手に処分したらまずい物も含まれる可能性があるので、上司に相談しながらの方が良いでしょう。
私物があるならば退職後に残っておくことのないように使わない物から徐々に持ち帰りましょう。
⑤取引先や社内関係者に挨拶しておく

退職前に取引先や社内関係者に挨拶をしておくと良いです。
各関係者への挨拶は直接話したり、メール、電話など、いろいろ方法はありますが、転職先が同じ業界ならばきちんとしておくと良いです。
全く違う業界に転職するなら最低限お世話になった人や気の合う人だけで良いので、あまり気にせずに済ませておきましょう。
⑥会社に提出物と返却物を渡す

退職前に会社に提出物と返却物がありますので、準備して渡しましょう。
基本的には上司や人事部から指示されるので、一般的なものをリストに記載しました。
- 退職届(退職願)
- 退職報告書
- 引継書
- 社員証
- 社章
- 制服
- 名刺
- 会社支給のPC、携帯電話
- 勤怠記録カード
- 会社のカギ、カードキーなど
制服は会社によっては退職後に洗濯して返却しなければいけないところもあります。
⑦有給休暇を申請する

退職日までの期間に有給休暇が残っている場合には申請をしましょう。
有給休暇は労働者の権利ですので、残っているならすべて使い切ってから退職する方が断然お得です。遠慮せずに使いましょう。
ここで注意したいのが、「余った有給休暇は会社が買い取ってくれる」という話がありますが、これは法律的には原則として違反となっています。
最後に
このページでは一般的な会社の退職の手順を解説しました。
ただ、このページで紹介した内容以上に実際の退職には勇気と体力が必要になってきます。
もし自分の力だけでは退職することが難しいと判断した場合には退職代行サービス業者に依頼するという手段もありますので、そちらを参考にしてみて下さい。
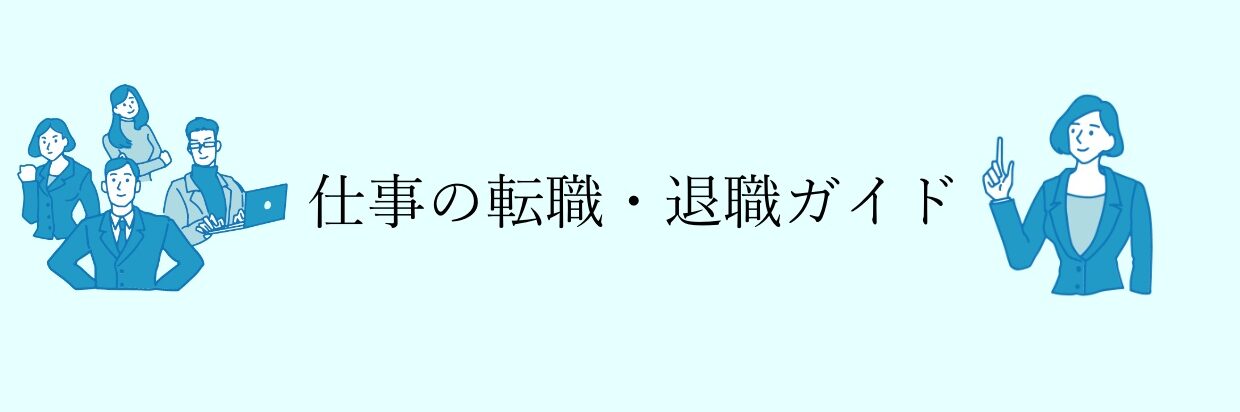
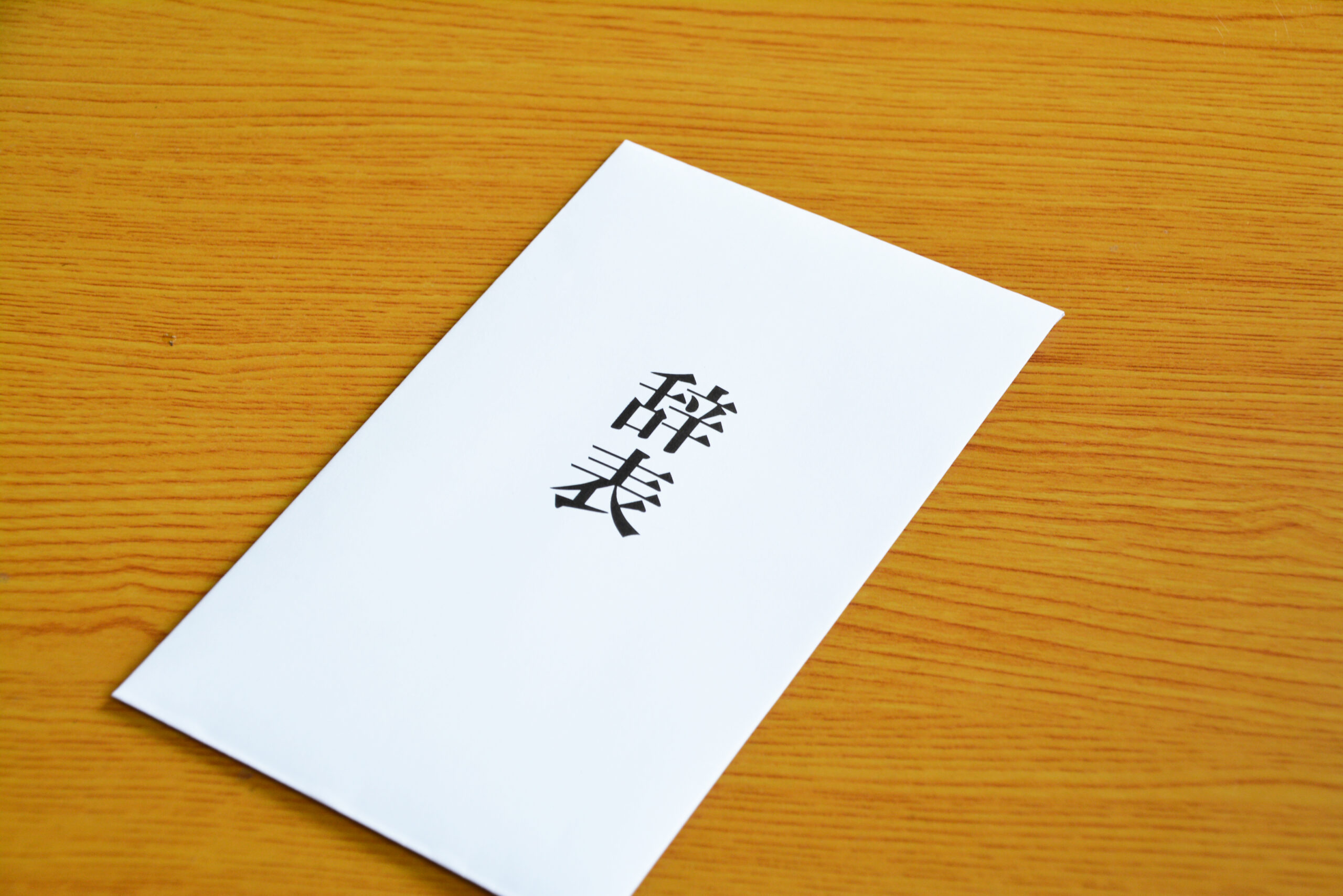

コメント